私たちの日常生活や仕事には、モチベーションが欠かせません。
しかし、「やる気が出ない」と感じることも少なくありません。
そんなときに役立つのが、社会心理学者ハイディ・グラント・ハルバーソン氏の著書『やる気が上がる8つのスイッチ』です。
本書は、やる気や目標達成について科学的な知見に基づいて解説した一冊です。
特に、「やる気の種類」と「人それぞれに適したアプローチ」が詳しく書かれており、自分に合ったやる気の出し方を見つけることができるでしょう。
本記事では、本書の概要を整理し、さらにモチベーションを高めるための3つの視点を考察していきます。
「やる気が上がる8つのスイッチ」の概要・要約
本書の基本的な立場
本書の主張は、「やる気を出すには万人に共通する方法はない」という点です。
その理由は、人の性格や考え方の傾向が異なるからです。
著者は、人を8つのタイプに分類し、それぞれに適したモチベーションのスイッチを提案しています。
これは、科学的な研究や実験に基づいた内容であり、非常に信頼性が高いと感じました。
やる気に関する3つの軸
本書では、やる気のメカニズムを理解するために、以下の3つの軸が重要だと述べています。
- マインドセット
考え方のクセを指します。
「照明マインドセット(他人に認められたい)」と「成長マインドセット(自分を成長させたい)」の2種類があり、成長マインドセットの方がやる気が持続しやすいとされています。
- やる気のフォーカス
目標達成に向けた動機の方向性です。
「獲得フォーカス(成功を追求する)」と「回避フォーカス(失敗を避ける)」の2種類があります。
どちらのフォーカスもチームや組織に必要とされています。
- 自信の有無
自信がある人の方が、やる気が持続しやすいです。
ただし、楽観的で根拠のない自信ではなく、「自分ならできる」という行動に結びつく自信が重要とされています。
8つのやる気タイプ
これら3つの軸を組み合わせることで、人は以下の8つのタイプに分類されます。
- 中二病(照明マインドセット×獲得フォーカス×自信なし)
- 臆病者(照明マインドセット×回避フォーカス×自信なし)
- うざいやつ(照明マインドセット×獲得フォーカス×自信あり)
- 退屈な人(照明マインドセット×回避フォーカス×自信あり)
- やる気の空回り(成長マインドセット×獲得フォーカス×自信なし)
- 真面目な見習い(成長マインドセット×回避フォーカス×自信なし)
- 新星(成長マインドセット×獲得フォーカス×自信あり)
- 熟練の匠(成長マインドセット×回避フォーカス×自信あり)
著者は、「新星」と「熟練の匠」を目指すべきだとしています。
この2つのタイプは、やる気が長続きし、成果を出す可能性が高いからです。
「やる気が上がる8つのスイッチ」における3つの考察
考察1:やる気を左右する「マインドセット」の違い
本書が最初に強調するのは、マインドセットの重要性です。
マインドセットとは、個人の考え方や思考のクセを指します。
著者は、「照明マインドセット」と「成長マインドセット」の2種類に分類し、やる気の持続性や質に大きな影響を与えると述べています。
照明マインドセットと成長マインドセットの違い
- 照明マインドセット
他人からの評価を重視し、成果を示すことで自分の価値を証明しようとする考え方です。
このマインドセットを持つ人は、結果に過剰に依存する傾向があり、うまくいかない場合にやる気を失いやすい特徴があります。
- 成長マインドセット
自分自身の成長や学びを重視する考え方です。
このタイプの人は、過程に価値を見出し、結果が伴わなくても成長を楽しむため、やる気を持続させやすいとされています。
成長マインドセットを持つための具体的な方法
成長マインドセットを形成するためには、以下のアプローチが有効です。
- 他人との比較を減らす
成果を他人と比較するのではなく、過去の自分と比較することを習慣化します。
「昨日の自分よりも成長しているか」を基準にすることで、内発的なモチベーションが高まります。
- 過程を評価する
結果だけでなく、そのプロセスで得られた経験やスキルに目を向けることが重要です。
たとえば、失敗したプロジェクトであっても「学びがあった」という視点を持つことで、やる気を次の挑戦に繋げられます。
私の体験談
私自身、仕事で結果を重視しすぎてしまい、うまくいかないときにモチベーションを失うことがありました。
しかし、過程を重視するよう意識を変えると、挑戦そのものを楽しめるようになり、結果的に成果も向上しました。
成長マインドセットを取り入れることで、継続的なやる気を保つことが可能だと実感しています。
考察2:やる気の方向性を決める「フォーカス」の重要性
次に注目すべきは、「やる気のフォーカス」という概念です。
フォーカスとは、やる気の向かう方向性を意味します。
これには「獲得フォーカス」と「回避フォーカス」の2種類があり、それぞれ異なる特性を持っています。
獲得フォーカスと回避フォーカス
- 獲得フォーカス
成功を目指し、ポジティブな成果を追求する方向性です。
挑戦することや新しいことに積極的で、リスクを恐れず行動します。
- 回避フォーカス
失敗を避けることを重視し、安定を求める方向性です。
リスクを回避し、慎重に計画を立てて行動する傾向があります。
フォーカスの違いがもたらす影響
フォーカスのタイプは、性格や状況によって異なりますが、どちらが優れているというわけではありません。
たとえば、革新が求められる場面では獲得フォーカスが有利ですが、リスク管理が重要な場面では回避フォーカスが役立ちます。
自分のフォーカスに合った環境を整える
フォーカスを活かすためには、自分のタイプを理解し、それに合った環境を作ることが大切です。
獲得フォーカスの人は、新しい挑戦が多い職場や自由度の高い環境が適しているでしょう。
一方、回避フォーカスの人には、安定した環境や具体的な指示がある職場が向いています。
考察3:「自信」の有無がモチベーションを左右する
最後に取り上げたいのが、「自信」の重要性です。
本書では、やる気を引き出す鍵として、「行動に繋がる自信」を持つことが挙げられています。
行動に結びつく自信とは
ただの楽観主義とは異なり、「自分ならやり遂げられる」という現実的な自信が必要です。
これは、過去の成功体験やスキルの向上を通じて培われるものです。
自信を高めるための具体的アプローチ
- スキルを磨く
やる気を出したい分野でスキルを高めることが、自信につながります。
たとえば、資格試験の勉強で知識を増やすことや、小さな目標を達成することが有効です。
- 成功体験を積む
大きな目標を達成する前に、小さな成功体験を積み重ねることで、徐々に自信を育てることができます。
これは、階段を一段ずつ上がるようなイメージです。
自信を失わないための工夫
私も過去に大きな失敗を経験したとき、一時的に自信を失いました。
その際、小さな成功体験を意識的に積み重ねることで、「自分ならできる」という感覚を取り戻しました。
これは、本書で述べられる「自信の回復」の重要性を体感した瞬間でした。
まとめ
『やる気が上がる8つのスイッチ』は、モチベーションに関する新しい視点を提供する一冊です。
やる気を高めるためには、自分がどのタイプに属するのかを知り、適切な対策を取ることが重要です。
以下の3つの視点が特に印象的でした。
- マインドセットの転換
他人との比較を控え、理想の自分や過去の自分と比較することで、成長マインドセットを保つことができます。
これにより、やる気が持続しやすくなります。
- 自信を育む方法
自信をつけるには、スキルを磨き、小さな成功体験を積み重ねることが大切です。
「できる」という感覚がやる気を後押しします。
- 環境を整えること
自分のやる気のフォーカス(獲得型か回避型か)を理解し、それに合った環境を作ることが、ストレスを軽減し、成果を最大化します。
本書の考察を実生活や仕事に応用すれば、モチベーションの維持や向上が図れるはずです。
特に、「やる気が続かない」と悩んでいる方にとって、自分に合ったやり方を見つけるきっかけになるでしょう。
ぜひ本書を手に取り、自分に合ったモチベーションのスイッチを探してみてください。
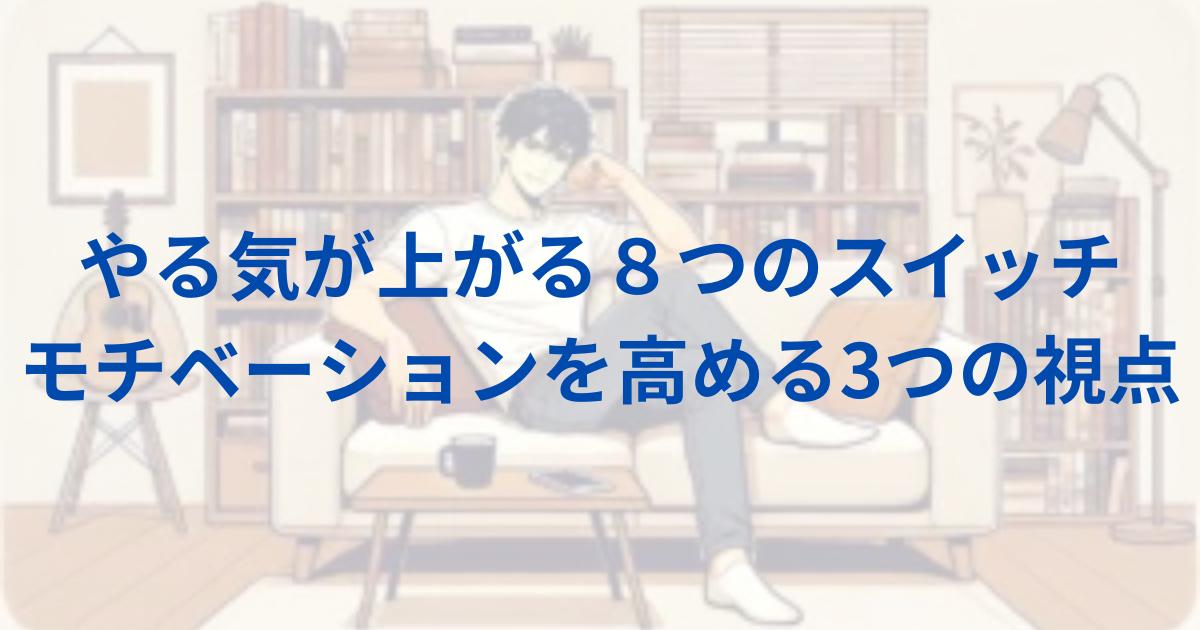
コメント